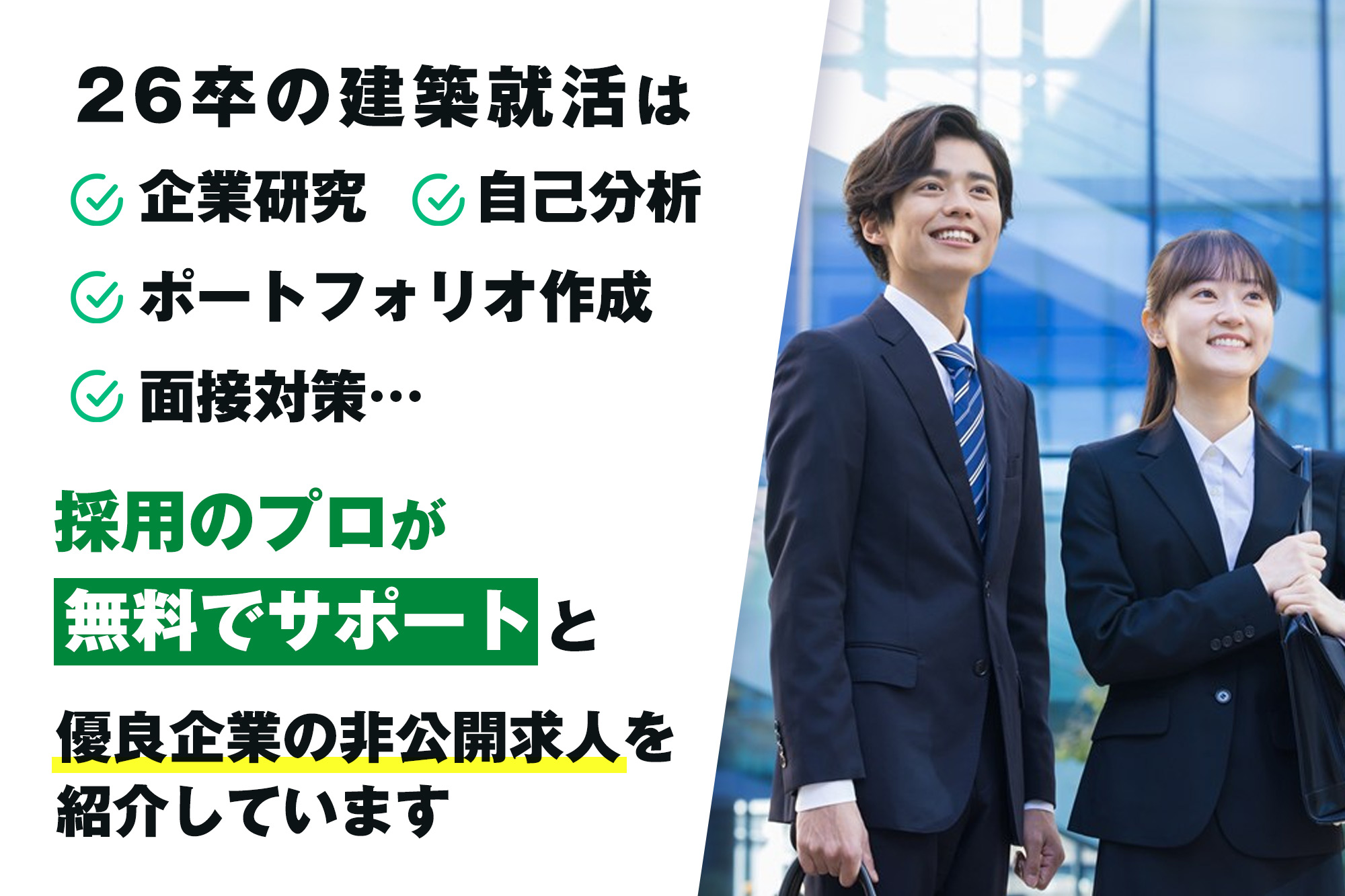3,265人の方が、この記事を参考にしています。
就活は多くの学生にとって大きなイベントですよね。将来を大きく左右するターニングポイントのひとつなので、不安を感じている方も多いことでしょう。しかし、就活は先輩社員に話を聞ける貴重な機会でもあり、しっかりと取り組むことで後悔のない決断をできるようになります。
この記事では、建築関係の会社における就活対策について解説します。ご紹介するのは一般的な内容で、個々の対策は企業研究で調査する必要がありますが、この記事を参考にしながら準備を進めてみてください。
目次
はじめに:建築関係の会社の就活で意識しておくこと
建設業界の就職活動について詳しく解説する前に、念頭に置いておくべきポイントをお伝えしたいと思います。
「建設業界」と一口に言っても、なかにはゼネコン・組織設計事務所・ディベロッパー・メーカーなどさまざまな種類の企業があり、就職活動の時期や流れはそれぞれ異なります。
また、建設業界のなかでも大組織であるゼネコンは「日本建設業会連合会(以下、日建連)」と呼ばれる連合組織の方針に従って採用活動を行うのが基本ですが、実際は日建連に定められたスケジュールより早い段階で採用活動の準備を進めているケースがあります。
以上のことから、インターネットで調べた情報だけでは個々の会社の採用活動について詳しく知るのは難しいのが実情です。可能であれば、大学の教授・先輩のつながりを頼りにOB・OGの話を聞かせてもらうことをおすすめします。
建設業界の就活時期は早い
建設業界の採用活動は他の業界と比べて動き出しが早い傾向あります。特にゼネコンの採用活動の早期化が学生の勉学の妨げになると懸念されており、政府は日建連を通して採用活動の開始日を定めています*1。以下は2024年卒の日程ですが、年度によって変更になる可能性があるのでチェックしておきましょう。
【2024(令和6)年度卒業・修了予定者を対象としたゼネコンの就職・採用活動日程】
- 広報活動開始:卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降
- 採用選考活動開始:卒業・修了年度に入る直前の6月1日以降
- 正式な内定日:卒業・修了年度に入る直前の10月1日以降
企業によっては大学3年生及び大学院1年生を対象に夏頃からインターンシップを実施しています。学生が実際の仕事に触れることが主な目的ですが、企業としては前もって優秀な学生を知るよい機会です。採用活動はまだ先のことと思うかもしれませんが、積極的に参加することをおすすめします。
*1 出所)日本建設業連合会「 2024(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について」
就活に向けた準備
次に就活に向けた準備について解説します。
自己分析
まずはしっかりと自己分析を行いましょう。自分の半生を振り返り、今の自分がどのような人間か、これからどのようになりたいかを整理します。具体的には以下のようなことを見つめ直してみてください。
- 幼少期の性格
- 成長過程
- 性格・考え方の変化
- 変化を与えたターニングポイントとそのときの心境
- 将来やりたいこと
- 将来に向けて学生の間に学んだこと
- 学びを共有した仲間
- 仲間のなかでの自分の立場・役割
業界・企業研究
しっかりと自分を見つめ直すことができたら、業界・企業研究を行います。ここで大切なのは、「業界」と「企業」のそれぞれについて詳しく知ることです。企業が求めているのは、「業界」に入りたい人間ではなく、その「企業」に入りたい人間だからです。エントリーシートや面接で「企業の特性」に着目してアプローチできるように研究を行いましょう。
【業界研究のポイント】
- 業界全体の事業・サービス
- プロジェクトの進め方、ステークホルダー
- 社会的な責任・役割
- 世界の同じ業界と比較した日本の建設業界の姿
- 目指している将来像
【企業研究のポイント】
- 経営理念
- 企業風土
- 代表プロジェクト
- 建物のデザイン・空間構成・環境性能などの特徴
- 目指している将来像
- 求めている人材
- 働き方
基本的にはインターネットで情報を集めることになりますが、実際に建物を巡ったりOB・OGの話を聞いたりしてリアルな体験ができると、表現の具体性がアップしてアピールしやすくなります。
エントリーシート・ポートフォリオの作成
建設業界においても就活の第一関門はエントリーシートなどの書類選考が一般的です。自己分析及び業界・企業研究で考えたことをわかりやすく表現しましょう。
大切なのは、企業の特徴や目指している将来像に、自己分析で見えてきた自分の良さを結び付け、役に立つ人材であることをアピールすることです。「ものづくり」「建築」「代表プロジェクトの名称」などをキーワードとして散りばめ、建設業界やその企業に対する熱い思いを伝えます。
エントリーシートで書いた内容は次の面接で質問を受ける可能性があります。曖昧な表現がないか、しっかりと受け答えできる内容になっているのかを確認してから提出しましょう。
設計職を例に志望動機の書き方について以下の記事で詳しく解説していますので、こちらも参考になさってください。
企業や職種によってはポートフォリオを要求されることがあります。フォーマットに従いながら課題や作品をわかりやすくまとめ、どのようなことを考えて取り組んだかを振り返っておきましょう。
面接対策
面接では面接官の目を見てハキハキと受け答えすることが大切です。当たり前のように聞こえるかもしれませんが、多くの学生にとって立派な社会人である面接官と対等に話をするのは難しいものです。
まずはエントリーシートをもとに想定質問を考え、スムーズに答える練習をしましょう。頭のなかで繰り返すだけでなく、しっかり声に出すようにしてください。本番は緊張で声が小さくなりがちなので、練習のときから大きめの声を意識するのがポイントです。
本番はいくつか想定外の質問をされるでしょう。より深く、具体的に自己分析と業界・企業研究を行うことで自分らしい適切な回答の引き出しが増えていきます。普段から自己分析のクセが付いている人は、どのようなときでも自分らしい受け答えができるものです。
グループディスカッション対策
技術系では少ないですが、職種によってはグループディスカッションが行われます。課題についてグループでディスカッションをして成果を発表する、というのが一般的な流れです。
人によってアピールポイントは異なりますが、以下のような姿勢が評価されます。チームワークを意識して取り組みましょう。
- 根拠を明確にして自分の意見をしっかり発言する
- 人の意見を聞いて正しく解釈する
- 発言が少ない人に意見を求めてチームワークを高める
- 図などを使って議論の内容をわかりやすく表現する
- 与えられた役割を果たす
インターンシップが重要な企業もある
なかにはインターンシップを重要な採用活動の一環と捉えている企業もあります。ここではインターンシップについて解説します。
採用との関係性
インターンシップは学生のキャリア形成支援が主な目的ですが、就職・採用活動の開始日より前にインターンシップと称して実質的な採用選考活動が行われる実態があったようです*1。政府は日建連を通してこのような実態が学生に混乱を与え、学業に悪影響を与えないように改善を要請していますが、しばらくはインターンシップが採用につながる可能性があると考えておいた方がよいかもしれません。
時期・期間
インターンシップの時期や期間は企業によってさまざまです。一般的には夏・秋・冬といったタームで実施されています。1日で終わるものから1週間かけて行うものまであるので、企業のホームページや就職情報サイトを参考にスケジュールを調整しておきましょう。
職務体験の内容
インターンシップの職務体験には以下のようなものがあります。
- 先輩社員の実務の支援
- 先輩社員とのディスカッション
- 模型・CGスタディ
- 設計課題
- グループワーク
- 現場見学・実習
企業の種類ごとの特徴
最後に、建設業界の企業の種類ごとの特徴を簡単にご紹介します。
ゼネコン
ゼネコンは、建設プロジェクトの企画・設計から施工までを総合的に請け負う企業です。設計・施工部門をはじめとする内勤・外勤部門を持つ大きな組織であり、建設業界で大きな存在感を放っています。基本的には「建物を施工する」ことで報酬を受け取っており、建設業界のなかでも特にものづくりに特化した企業といえます。
組織設計事務所
組織設計事務所は設計・監理業務を生業とする企業です。設計のプロとして高いデザイン・企画力を強みにしており、多くの有名建築物を手掛けています。設計者としてのセンスやデザイン力に自信があり、設計に専念したい方におすすめです。
ハウスメーカー
ハウスメーカーは全国規模で住宅を提供するメーカーです。戸建て住宅を主力商品とする企業が多いですが、分譲マンションや賃貸住宅、物流倉庫などを扱っているケースもあります。住宅業界はエンドユーザーが近く、暮らしに寄り添った仕事に携われます。
ディベロッパー
ディベロッパーは、土地や街の開発事業者です。近年は大規模マンション・複合商業施設・都市再開発などが活発に進められており、建設業界におけるディベロッパーの存在感が年々増しています。ディベロッパーは街づくりの事業者としてプロジェクトを牽引できる大きなやりがいが魅力です。
おすすめの就活エージェント
最後に、おすすめの就活エージェントをいくつかご紹介します。自分ひとりで就活を進めることに不安を感じている方や、客観的なアドバイスを求めている方は利用してみてください。
コンキャリ建築土木
コンキャリ建築土木は、建築・土木分野の学生に特化した就活支援サービスです。情報不足に悩む建築土木学生のために、各学生の状況や志望領域に合わせて平均5社以上のスカウトを提供する点が最大の特徴です。建築土木領域専門のアドバイザーが自己分析からES・面接対策まで全面的にサポートし、業界特化型のカンファレンスや選考対策イベントも多数開催しています。
毎月8,000人が利用する実績を誇り、東京大学をはじめとする全国の大学・専門学校からの多くの方が利用しています。就活初心者から上級者までどのフェーズでも利用可能なので、建築土木業界での就職を目指す学生にとって心強いパートナーとなるでしょう。
公式サイト:コンキャリ建築土木
ジョブコミット
ジョブコミットは、HR team株式会社が運営する新卒就活支援サービスです。専任のエージェントが学生一人ひとりの未来像を明確にし、自己実現を第一に考えたサポートを提供しているのが特徴です。ES作成から企業ごとの面接対策まで、内定獲得に向けて徹底的にサポートしてくれます。
学生に寄り添った親身なコンサルティングを心がけ、「就職相談に本気で向き合ってる会社」「本当に信頼できる人材紹介会社」「申請丁寧な人材紹介会社」の3部門において1位を獲得しています。単なる内定獲得ではなく、本当に望むキャリア形成を目指す就活生におすすめのサービスです。
公式サイト:ジョブコミット
キャリセン就活
キャリセン就活は、シンクエージェント株式会社が運営する新卒専門の就活エージェントサービスです。総合職を目指す学生向けに、専属のキャリアアドバイザーが企業紹介から内定まで全面的にサポートしてくれるのが特徴。ナビサイトでは出会えない新進気鋭のベンチャー企業や業界トップシェアの優良企業のほか、早期内定獲得が狙える非公開の特別先行枠を紹介してくれます。
無料インターン「TECH-BASE」やAI面接対策サービス「RECOMEN」など、就活対策スキルを向上させるツールも充実しており、学生の成長と内定獲得を多角的にサポートしてくれる総合的な就活支援サービスです。
公式サイト:キャリセン就活
就活は準備が大切です。特に自己分析や業界・企業分析といったインプットをしっかり行うことで、自分らしさを表現しながら企業に役立つ人材であることをアピールできるようになります。苦しい場面があるかもしれませんが、よい機会ですので今までの自分を見つめ直して理想の将来像を思い描き、積極的に取り組んでいきましょう。
なお、建築転職でも建築業界に特化した就活エージェントサービス「建築就活」をご用意しています。ご興味のある方はぜひ無料登録から!
まとめ
- 東急不動産ホールディングスやダイビルのような上位企業では平均年収1,000万円を超える一方、一般的なビル管理業務中心の企業では全国平均を下回るケースもあり、企業選択が年収に大きく影響する
- 宅地建物取引士、マンション管理士、賃貸不動産経営管理士などの国家資格は、高年収を実現するのに役立つスキルであり、キャリアアップの重要なポイント
- 不動産管理業界は業務内容が多岐にわたるため、転職エージェントに相談することで自分の能力・希望に合った企業を効率的に見つけられる
不動産管理業界は幅広い人材が活躍できる分野です。適切な情報収集と戦略的なキャリア形成により、理想の働き方と年収を実現しましょう。
この記事を監修した人

株式会社トップリフォームPLUS
取締役
小森 武
保有資格:1級施工管理技士・一級建築士
最後までお読みいただきありがとうございます。
建築転職に無料登録いただくと
- 表には出ていない、各企業・職場のリアルな情報
- 年収750万円以上の非公開求人情報
がもらえます。
まだ転職を決めていなくても利用できますので、
ぜひご活用ください。