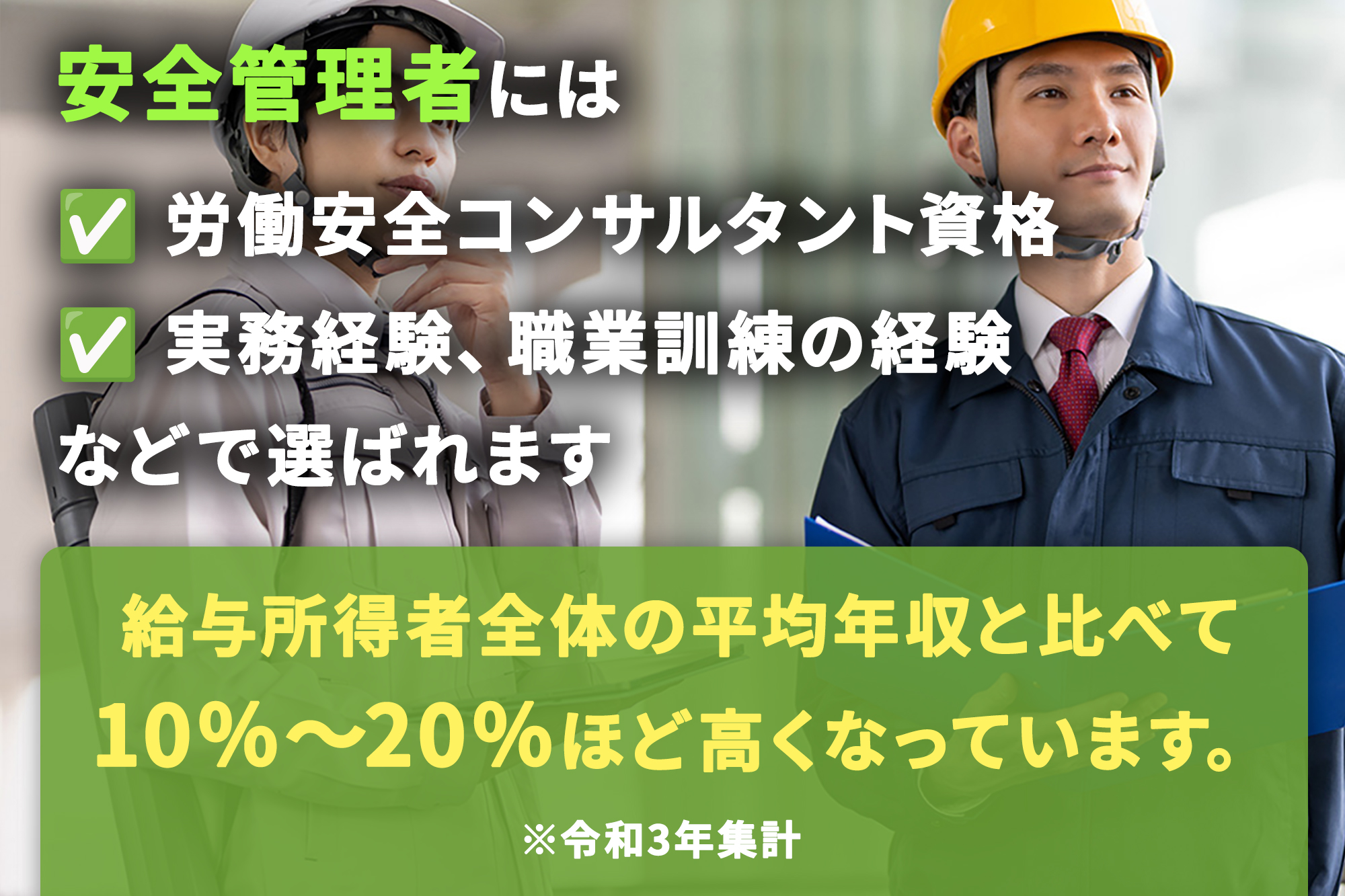11,684人の方が、この記事を参考にしています。
この記事をご覧の方のなかには、職場で「安全管理者」という名前を見聞きした方もいるでしょう。安全管理者は仕事を安全に進めるうえで、重要な役割を果たします。法令により、安全管理者の配置が義務となっている職種も多数あります。
安全管理者はどのような方が選任され、どのような仕事をするのでしょうか。また選任される際に必要な研修は、どのような内容でしょうか。この記事では安全管理者の職務内容や資格の取得要件、選任時研修を中心に解説します。
目次
安全管理者とはどのような資格か?
安全管理者は、職場の安全を守るための資格です。職場によっては以下のとおり、さまざまな危険が潜む場合もあります。安全管理者の資格を持つ方は、これらの重大な事態を防ぐために必要な対応を行うのが仕事です。
- 機械に手や足を挟まれ、けがをする
- 什器が倒れ、下敷きになる
- 設備が破損し、周辺に被害をおよぼす
- 有害物質や酸欠により、命を失う
企業で労災事故が起こると、さまざまな不利益をこうむりかねません。安全管理者は、働く方だけでなく企業も守るうえで重要な役割を果たします。
安全管理者と衛生管理者との相違点
職場では衛生管理者もよく配置されます。安全管理者との違いは、どこにあるのでしょうか。
安全管理者は事故を未然に防ぎ、安全に作業を遂行できるよう、職場の環境を整える役割を担います。
一方で衛生管理者は労働者の健康や労働環境の改善など、衛生的で働きやすい環境を実現する役割を担う職です。
ちなみに、安全管理者と衛生管理者は兼任できますが、両方を一人でこなすには職務量が多すぎて業務に支障が出る可能性がありますし、一人で抱える責任も重くなるため、それぞれ専任者を立てるほうがよいでしょう。
総括安全衛生管理者とは
一定規模以上(建設業は常時使用する労働者数が100人以上)の事業場においては、「総括安全衛生管理者」の選任が義務づけられています。総括安全衛生管理者は、安全管理者と衛生管理者を指揮し、労働者の危険と健康障害を防止する役割を果たします。
選任すべき者の資格要件は「当該事業場において、その事業の実施を実質的統括管理する権限及び責任を有する者(工場長など)」とされ、安全管理者や衛生管理者とは異なり学歴要件などはありません。建設現場においては現場所長が担当するのが一般的です。
大きな建設現場においては、現場所長(総括安全衛生管理者)の指揮のもとで安全管理を行うことになることを意識しておきましょう。
安全管理者の職務内容
安全管理者は職場の安全を管理し、必要に応じて適切な措置を講じる職責を担います。以下の仕事は、安全管理者の代表的な職務です。
- 職場で危険な状況を発見した際に、応急処置や事故防止の措置を講じる
- 設備や器具の定期点検や整備を行う
- 作業の安全に関する教育や訓練を実施する
- 安全衛生に関する方針の表明、計画の作成や実施、結果の評価や改善を行う
- 災害が発生した場合、原因の調査や対策を検討する
- 作業主任者や安全に関する補助者を監督する
- 安全に関する資料の作成や収集、重要事項を記録する
安全管理者は、単に職場の安全を守ることにとどまりません。これまでの職場環境を評価し、安全な職場を作る役割も求められる職務です。安全管理者が職責をまっとうすることにより、安心して働ける職場となるのです。
なお安全管理者の職務の詳細は、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」の「安全管理者」ページに掲載されています。
安全管理者の選任を要する業種
安全管理者を選任しなければならない業種は、数多くあります。厚生労働省では安全管理者の選任を要する業種を、以下のとおり示しています。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
上記で挙げた業種に該当する企業で、常時50人以上の労働者を使用する事業場がある場合、事業場ごとに安全管理者を選任する必要があります。例えば東京支店、大阪支店、名古屋支店、茨城工場がある場合(各拠点とも労働者は50人以上)は、4箇所とも安全管理者を選任しなければなりません。
加えて事業場で働く労働者の数によっては、専任の安全管理者を配置する必要があります。該当する業種と労働者数は、以下のとおりです。
| 業種 | 常時使用する労働者数 |
|---|---|
| 建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 | 300人以上 |
| 無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 | 500人以上 |
| 紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 | 1,000人以上 |
| 選任が必要な業種で上記以外のもの ただし、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る |
2,000人以上 |
安全管理者の選任を要する業種は多いものの、専任とすることまで求められる業種は多くありません。例えば、ガス業や各種商品小売業は事業所の規模や働く人の数に関わらず、安全管理者は専任でなくてもよいとされています。しかしこのような事業所でも以下の条件を両方満たす場合は、専任の安全管理者を置くように求められるので注意してください。
- 労働者数が2,000人以上の規模となった
- 過去3年の間に労災の対象となった方が100人を超えた

安全管理者の資格取得に必要な要件を解説
安全管理者に選任される資格を得る要件は、大きく3つに分かれます。満たすべき要件はなにか、ケース別に確認していきましょう。
その1:労働安全コンサルタントの資格をお持ちの場合
労働安全コンサルタントの資格をお持ちの方は、安全管理者に選任される資格があります。特に受けるべき研修や、追加で取得すべき資格はありません。
労働安全コンサルタントの資格内容や取得方法は、以下の記事で詳しく解説しています。
その2:産業安全の実務経験により選任を目指す場合
産業安全の実務経験を積むことでも、安全管理者の資格を得られます。必要な実務経験の年数は、学歴や学んだ内容により異なります。以下の表でご確認ください。
| 学歴 | 理科系統の課程や学科を卒業 | 理科系統以外の課程や学科を卒業 |
|---|---|---|
| 大学 高等専門学校 |
2年以上 | 4年以上 |
| 高校 中等教育学校 |
4年以上 | 6年以上 |
上記の表に該当しない方でも7年以上の産業安全の実務経験をお持ちの方は、学歴にかかわらず安全管理者になる資格を得ます。
ところで産業安全の実務経験に含まれる業務は、さまざまです。安全管理の業務はもちろん、工場などで作業管理や工程管理に関わる業務も含まれます。「これまでの経歴をチェックすると、該当する仕事が思いのほか多かった」という方もいるのではないでしょうか。
その3:職業訓練を修了した方の場合
職業訓練を修了した方の場合、学んだ内容によっては産業安全の実務経験年数を短くできる場合があります。対象となる職業訓練の場合、以下に示す年数の実務経験があれば安全管理者に選任される資格を得ます。なお受講した職業訓練が対象になるかどうかは、事前にご確認ください。
| 職業訓練の種類 | 産業安全の実務経験年数 |
|---|---|
| 高度職業訓練 | 2年以上 |
| 普通職業訓練 | 4年以上 |
安全管理者選任時研修とは
安全管理者選任時研修は、安全管理者になる方が受講する研修です。受講にあたり、事前に「安全管理者の資格取得に必要な要件を解説」で解説した要件を満たす必要はありません。誰でも受講できますが、要件を満たすまでは研修を修了しても安全管理者にはなれないので注意してください。
研修では、以下の項目を学びます。
| 科目 | 所要時間 |
|---|---|
| 安全管理 | 3時間 |
| 安全教育 | 1時間30分 |
| 関係法令 | 1時間30分 |
| 危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置等 | 3時間 |
合計9時間にわたる研修を、1日から2日で実施します。2日間で行う場合は、ある程度余裕を持ったスケジュールとなるでしょう。その一方、1日で終える研修に参加する場合は朝から夜まで、長時間にわたる受講が必要です。
研修は複数の研修機関が実施しており、任意の申込み先を選べます。ただ、頻繁に開催されている研修ではないため、あなたのスケジュールに合った研修機関へ申込むことになるでしょう。
研修では職場の安全について、さまざまな観点から学びます。一例として安全管理者の役割や作業標準の作成、労働安全衛生マネジメントシステムが挙げられます。すべてのカリキュラムが終了すると、修了証が交付されます。
安全管理者の取得難易度
すでに労働安全コンサルタントの資格をお持ちの方を除き、安全管理者は「産業安全の実務経験」と「安全管理者選任時研修」の受講で選任される資格を得ます。実務経験をお持ちの方であればあとは研修の受講で済むため、難しい資格とはいえません。
むしろ「産業安全の実務経験」をどう積むかという点が、資格を取得するうえでのハードルになるでしょう。せっかく産業安全に関する職務に就くことができても、良い成果を挙げられなければ他の職種に異動となりかねません。必要な年数の実務経験を積むためには、日々の仕事に真摯に取り組み、確かな成果を挙げることが求められます。
安全管理者の転職先の例
安全管理者は、多くの業種で法令により配置が義務付けられています。このため、さまざまな会社で役立ちます。代表的な転職先を、以下に挙げました。
- 建設業
- 電気業
- 水道業
- 通信業
「安全管理者の選任を要する業種」でも解説したとおり、これらの会社では50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、安全管理者を選ぶ必要があります。特に労働者の数が300人以上の建設会社では、安全管理者は専任でなければなりません。拠点が多い会社では、多くの安全管理者が求められるというわけです。
安全管理者の平均年収
求人ボックスでは、安全管理者の平均月給を公表しています。地域によって異なりますが、平均月給額は36万円~38万円前後です。ボーナスを2カ月分と仮定すると、平均年収は500万円~530万円程度となるでしょう。経験がありスキルが高い方は、より高い年収が期待できます。
国税庁は「令和3年分 民間給与実態統計調査」において、給与所得者の平均年収が443万円であると公表しました。安全管理者の平均年収は、給与所得者全体の平均年収と比べて10%~20%ほど高くなっています。
まとめ
- 安全管理者は、職場の事故防止と安全環境の構築を担う重要な役割で、建設業や製造業など多くの業種で法令により配置が義務付けられている
- 資格取得には、「労働安全コンサルタント資格の保有」または「学歴に応じた産業安全の実務経験」に加え、「安全管理者選任時研修の受講」が必要
- 平均年収は500万円〜530万円程度と一般的な給与水準より高く、多くの業種で需要があるため転職先の選択肢が豊富
安全管理者は、働く人々の命と健康を守る大切な職務であり、企業にとっても労災事故を防ぐ重要な役割を果たします。職場の安全に関する実務経験を積み重ねながら、着実にキャリアを築いていくことで、多くの仲間の健康を守ることができる安全管理者になれるでしょう。
この記事を監修した人

株式会社トップリフォームPLUS
取締役
小森 武
保有資格:1級施工管理技士・一級建築士
最後までお読みいただきありがとうございます。
建築転職に無料登録いただくと
- 表には出ていない、各企業・職場のリアルな情報
- 年収750万円以上の非公開求人情報
がもらえます。
まだ転職を決めていなくても利用できますので、
ぜひご活用ください。